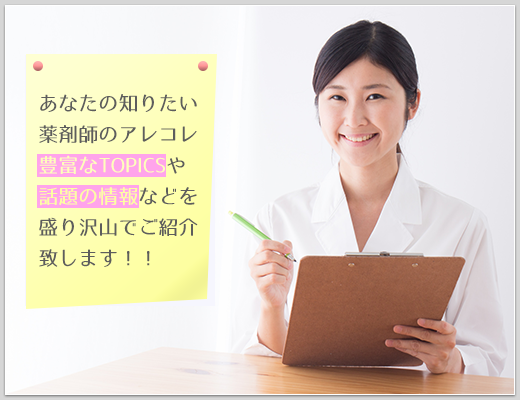
2024年08月11日
人口減少が今後も継続していくとはいえ、社会の高齢化も進んで行くので様々な疾患を抱えて病院通いする高齢者も増えていくことが予想されています。誰でも高齢になるに従い、複数の疾患を抱えてもやむを得ない面があると考えられているので色々な医療機関に出向く高齢者も増える傾向だということでしょう。
高齢化社会ではいくつもの病を抱える高齢者の増えることが避けがたいようなので医療機関の発行する患者の処方箋件数も増加の一途を辿ると見込まれてきました。一方で、2023年1月から医療機関と薬局の間に電子処方箋システムが導入され、人手を介するより処方箋の迅速処理が可能になりました。
このシステムを導入した調剤薬局の待合室では患者が待たされる時間の削減につながっているはずです。また、このタイミングに合わせるように調剤薬局の数が全国的にほぼ飽和状態になったといわれています。今後、手作業が多くて生産性の低かった調剤業務が変革する段階を迎えるきっかけになりました。
。
昨今まで薬局内の薬剤棚から必要な薬剤をピッキングし、必要な錠数を取り出して包装するなど、調剤業務が単純作業な割りに多忙なため調剤薬局が増え続けたわけです。このため、薬剤師の求人募集では応募者の引っ張りだこ状態が何年も続きました。
ところが、調剤薬局の設置がほぼ飽和状態になった途端に調剤業務へのロボット導入やネット薬局が話題になり始めたわけです。国内では調剤業務を一気にロボットで代替できる自動化技術力があるものの、設備入れ替え環境がまだ整っているわけでありません。
今後はロボットの導入状況次第で手作業だった調剤業務の自動化が急速に進み始める潮目が訪れそうです。
そうなれば調剤薬局において手作業による調剤業務減少による調剤従事者の負担軽減や人的調剤ミス削減及び労働生産性の向上実現という大命題が表面化します。そこで、このようなロボット導入ステージが広がれば薬剤師がもっと医師や患者と直接向き合える時間が増えて患者とのコミュニケーション不足の解消につながるはずです。
患者の在宅看護が大幅に増える時代を迎えて今後、患者宅へ出向いて処方されている薬剤と患者の病状や体調とのマッチングを注視していけるスキル活用を担っているはずです。元々、薬剤師は薬品取り扱いの専門家として処方薬に対する薬品原材料の特徴などを医師にアドバイスできる立場ですから。
患者への服薬指導や医療機関への医薬品に関するアドバイスなどこそこの分野の専門家が本来目指すべき業務だといわれているわけです。